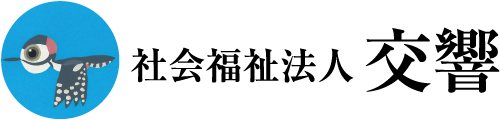第二回 障害のある子どもの18歳の壁

子どもが18歳になると、それまでは主に児童福祉法の枠組みの中で受けていた福祉支援サービスは大人と同じ障害者総合支援法の枠組みの中でのサービスに変わります。それによって、受けることのできるサービスの内容が変わるため、子どもも親も生活の見直しをせざるを得なくなってしまいます。
特別支援学校を卒業する時の18歳の壁について
障害のある子どもが特別支援学校高等部を卒業する時の「18歳の壁」という言葉をご存じですか?保育園や幼稚園を卒業し、小学校に入学する時に親が直面する小1の壁(第88 回コラム 小1の壁と学童保育を参照ください)と同じように、家族がそれまでと同じように仕事を続けることができるか、働き方をどう見直すかの判断を迫られることを示す言葉です。
障害のある子どもの数は増えている
令和5年版の文部科学省からの統計によれば、幼稚部から高等部の特別支援学校に通っている児童・生徒数は148,635人で、高等部の生徒数は65,355人と報告されています。少子化で子どもの数は減っていますが、障害のある児童・生徒の数は増加傾向にあります。
1955年には5,300人であった高等部の生徒数は、2015年以降、6万人を超え、特別支援学校卒業の際に18歳の壁に突き当たり悩む親がたくさんいます。

18歳までの支援サービスは児童福祉法の枠組みで行われる
18歳までの子どもの障害福祉サービスの内容は主に児童福祉法で定められています。
子どもに対する支援としては、小学校に入学する6歳までは、「児童発達支援」という福祉サービス(第70回 子どもの発達支援と障害福祉サービスを参照ください)があります。
この支援サービスは子どもの障害の特性に合わせた遊びや学習を通じて小学校で生活を行っていくのに必要な自立への支援や機能訓練を行うものです。
また、特別支援学校に通っている18歳までの障害児には放課後等デイサービス(第87回 子どもと教育-放課後等デイサービスを参照ください)という支援があります。
この支援サービスは健康状態の維持や運動能力の改善だけでなく、周りの環境に対する適切な認知と行動、コミュニケーションと言葉、集団参加など周りの人との関わりや情緒の安定など将来の自立に必要な支援です。
子どもが特別支援学校に通っている18歳までの間は、授業が終わると放課後等デイサービスの事業所から学校に送迎の車がきますので、放課後は学校から事業所に通うという流れができています。この放課後等デイサービスがあることによって、子どもは放課後の時間に療育や支援を受けることができ、保護者も安心して働くことができます。放課後等デイサービスは、保護者が安心して仕事が続けることができる学童保育と同じ役割を果たしているのです。
また、夏休みなどの長期休暇も放課後等デイサービスを使うことによって、18歳までは朝から18時くらいまで子どもを預かってもらうことができます。
18歳以降の支援サービスの内容は障害者総合支援法の枠組みに変わる
18歳を迎え特別支援学校を卒業すると、受けることができる支援サービスが児童福祉法の枠組みから障害者総合支援法の枠組みに変わるため、それまで利用していた放課後等デイサービスなどの福祉サービスは利用できなくなります。
そのため、特別支援学校を卒業した18歳以降は、障害者総合支援法に基づく介護サービスなどを提供している通所型の生活介護事業所に切り替わることになりますが、事業所の場所や送迎の条件など選択肢が限られ、定員に空きがなければ利用することはできません。
また、生活介護のサービスでは、サービスを受けることができる時間は、午前9時からおおよそ午後3時頃までが多く、送迎を含めて16時~16時半位に帰宅する場合がほとんどで、今までの放課後等デイサービスに比べて預かってもらえる時間が短くなるため、ご両親は今までと同じような時間帯で働くことが難しくなる可能性があります。
また、夏休みなどの長期休暇も18歳までは放課後等デイサービスを使い、朝から18時くらいまで預かってもらうことができましたが、18歳以降はそれができません。
お子さん自身も人との交流の機会が減ってしまうだけでなく、ご両親の負担も増え、働くことを制限しなければならなくなってしまいます。

障害のある18歳以降の子どもの夕方の支援としては?
放課後等デイサービスと同じような夕方までの時間帯の支援としては、障害のある人を日常的にサポートする地域の日中一時支援や移動支援、地域活動支援センターなどによる支援があります。
しかし、これらは放課後等デイサービスとは違い、地域生活支援事業と呼ばれる地域に密着した市町村の事業であるため、提供されるサービス内容や質は住んでいる地域によって差があり、夕方の支援は必ずしも保障されているとは限りません。
日中一時支援のサービスは自治体によって月に利用できる日数は違いますが、大半は利用時間が自由に選べ、遅くまで障害者を預かってもらうことが可能です。土日や祝日であっても利用することができる利点があり、使い勝手の良い支援ですが、預かってもらえる人数が限られており、報酬単価が低く運営している事業所は少ないのが現状で、ほとんどは放課後等デイのような送迎がありません。
生活介護と日中一時支援は併用することができますので、同じ日に生活介護の後に、日中一時支援の利用を組み合わせれば19時や20時頃まで預かってもらうことができます(第89回 重症心身障害児(者)と家族のレスパイトケアを参照ください)。
障害を持った子どもが18歳になる時に必要な手続き
18歳になり、障害者総合支援法に基づくサービスに移行し、自分が希望する自立支援給付サービスを受けるためには、本人の障害の程度の認定調査、医師意見書などを踏まえた障害支援区分の認定が必要で、審査の結果、サービスを受けるのに必要な受給者証が交付されます。
福祉サービスの体系は、訪問系・日中活動系・施設系に分かれる介護等給付と居住系・訓練系・就労系の訓練等給付に大別されています。
<生活に関する手続き>
➀障害者手帳の取得、更新は忘れずに行う
障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」があります(第71回コラム 子どもの障害福祉 -手帳、手当、年金―を参照ください)。
障害者手帳は18歳までは児童相談所などで、新規の取得や更新の手続きができましたが、18歳以降は市町村の障害福祉課で手続きを行い、再判定して手帳を更新することが必要となります。
障害者手帳の交付を受けると、生活の上で様々な割引や税金の減免、障害年金などの特典が得られます。20歳になって障害者年金の申請の際には障害者手帳が必要となります。
②自立訓練を受けられる
自立した生活ができるように、身体機能・生活能力の向上に必要なリハビリなどの訓練を受けることができます。自立訓練を受けるためには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
<仕事に関する手続き>
➀ハローワークに申請する
障害者枠での就職を希望する場合、ハローワークの障害者専門窓口で求職申込みをします。「求職申込書」を提出し、ハローワークカードを受け取ると利用ができます。
②就労支援を受ける
18歳から受けられる障害福祉サービスの中には、「就労支援」があり、障害の程度によって就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援の3種類に分けられています。
就労継続支援A型
一般企業への就職は難しい人で、事業所と雇用契約を結び、働いて給与を得ながら、訓練を受け、知識や能力を身につけます。
就労継続支援B型
就労継続支援A型の仕事が難しい人などが対象で、軽作業をしながら訓練を受け、できたものに対する成果報酬として賃金が支払われます。
就労移行支援
事業所で訓練を受けながら、一般企業への就労を目指す人が対象で、就職に重点を置いた支援を受けることができます。利用できる期間は2年で、就職先を探し、その後定着して職場で働くためのサポートも行なってくれます。
障害福祉サービスを受けるのに必要な受給者証を取得する手続きの流れ
自立訓練や就労支援を利用するには「障害福祉サービス受給証」が必要です。
市の福祉課へ相談し、受けたいサービスについての「支給申請書」を提出します。この申請書が受け付けられると、「サービス等利用計画依頼書」が交付されます。
この依頼書を相談支援事業所に提出し「サービス等利用計画案」を作成し市に提出します。

市はこの案を参考にして、「障害福祉サービス受給証」の交付を決定します。
就労支援を利用する場合には、仕事や支援の内容が本人の希望やスキルと合わないことを防ぐために一定期間、仕事の体験を行います。その後、相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を市が受理したら、障害福祉サービス受給証が正式に交付されます。手続きから交付まで、約1~2か月かかるとされていますので、18歳になったら早めに申請の手続きを行っておくことが大切です。
18歳の壁を乗り越えるには
障害を持つ子どもが18歳を迎え、社会に出ていくためには多くの支援が必要です。支援が減る中でも積極的に情報を集め様々なサービスを組み合わせることによって、その子が生きやすい居場所を見つけることが大切です。
地域の支援を活用する
18歳以降は、地域社会での支援がますます重要で、障害者相談支援事業所や福祉事務所など、自治体が提供しているサービスを利用することで、生活面での支援を受けることができます。
また、民間の支援団体やNPO法人なども、障害者支援を行っているところがあります。地域によって支援内容やサービスが違いますので、情報を集め利用できる支援を見つけることが大切です。
就労支援を利用する
18歳以上になると、就労支援が必要になります。障害にあった就労支援サービスもあり、相談支援事業所等に相談することで、障害を持ちながらも働くための支援を受けることができます。
生活支援サービスの活用
障害者の生活を支えるための支援として、家事援助等居宅介助や外出支援などの生活支援サービスを受けながらその子にあったより良い生き方を見つけることが大切です。
さいごに
18歳!
高校を卒業し進学や就職など一人で生きていく道を見つけていく時期です。子どもの障害と向き合ってこられたご両親はただただ一生懸命、毎日お子さんの成長を願って日々を過ごし来られたと思います。あっという間の18年だったかもしれませんね。その間にはつらさや悲しさ、くやしさなど言葉にできないたくさんの感情があったと思います。見えない未来への不安やストレスなど、思いが空回りしてしまいますよね。
障害があってもより多くの選択肢選べ、安心して生活できるように具体的な相談先や支援の流れを事前に知っておき、頼れる関係を作っておくことが、これからのお子さんに大切ではないかと思います。
周りには支援してくれる人達がいます。お母さんは一人じゃないよ。

ではまた。 By ばぁばみちこ