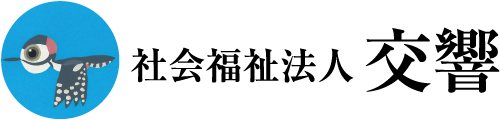第一回 出会いとさよならの続き

こんにちは。小児科医の林谷道子です。ここすまネットの活動終了に伴い、新しく社会福祉法人交響のホームページにお引越しをさせていただきました。
第一回は、今までの思いと、今、私が障害のある子どもたちのそばにたどり着いて、感じていることを書かせていただきたいと思います。
人生の中で、あの時、あの場所で、あの光景に出会わなかったら、自分の生き方は変わっていたかもしれないと感じることがある。しかし、一度見てしまって心に感じた出来事は決してなかったことにはできず、自分の生き方の中に何らかの影響を残していく。それはきっと運命と呼ばれるものだと思う。
私にとって、その光景は私が医師として新生児医療に携わり、その後たくさんの子ども達やご両親との出会いにつながるきっかけとなった。
そして今、私が重症心身障害児施設で子ども達のそばにいることは私にとって、今までの出会いの必然の結果だと感じている。
はじまり
私が医師になった1974年当時、広島では十分な新生児医療は行われていなかった。
研修医時代を過ごした広島大学の未熟児室にはいくつかの保育器があり、酸素投与や経管栄養が行われていたが、呼吸が悪い小さな未熟児はなす術もなく亡くなった。
私は研修医一年目の夏に、当時国内で先進的な新生児医療が行われていた名古屋市立大学の新生児集中治療室(NICU)を見学する機会があった。そこで、保育器の中で、手のひらに乗るくらいの小さな赤ちゃんが呼吸器をつけて生きている姿にカルチャーショックを受けた。病棟には大きく育って退院していった赤ちゃんの写真が飾られていた。それが新生児医療に携わるきっかけとなり、35年間の新生児医療の原点となった。この夏の運命的なめぐり合わせがなければ、新生児医療とは無縁であったかもしれないと思う。
広島市民病院での小児科医長との出会い
大学での二年の研修期間を終えて私は広島市民病院に配属された。その当時の市民病院の小児科医長は村上基千代先生であった。陸軍軍医を経験されており、確かビルマに行かれていたと聞いたことを覚えている。
とても親分肌の先生で「小児科医として何がやりたいのかね?」と聞かれ「私、広島の赤ちゃんを診たいんです。」と答えたのを覚えている。
その後、村上先生の英断で1979年に広島市民病院に初めてのNICUを備えた未熟児新生児センターが開設され、「広島の赤ちゃんを診たい。」という私の願いは叶えられることとなった。センター開設前からすすめた病棟の設計や新生児用のカルテ、看護記録、呼吸管理表、輸液表などの準備は大変であったが楽しいものであった。
新生児医療を始めた当時は、呼吸の悪い未熟児が産まれるとほとんど徹夜に近かったが、一つ一つが手探りであった分、小さかった赤ちゃんが元気に退院していく姿は私にとって何ものにも変えがたい大きな喜びであった。
新生児医療の中で感じたジレンマ
その後、日本の新生児医療は目覚ましく進歩し、小さな赤ちゃんや重い病気を持つ多くの赤ちゃんの命が救われた。一方、その影で亡くなっていく赤ちゃんとご両親、後遺症のために在宅医療を必要とする赤ちゃんとご両親にもたくさん出会った。
後遺症が残り、在宅医療が必要な赤ちゃんが退院していく時は、いつも「これで良かったのか?」という思いが私の心に残っていた。
在宅医療には長い入院生活を送ってきた子ども達が家族と暮せ、両親が子どもへの愛情と成長を実感できるメリットがある。しかし、現実には子どもの在宅医療を支えている基盤は非常にもろく、主なケアを担っているのはお母さんで、365日、24時間の休みのない献身的な努力によって、子どもたちは命を永らえているといっても過言ではない。
今、子どもへの虐待が問題になっているが、虐待は一歩間違えれば、障害のあるなしに関らず、多くのお母さんにその危険性がある。お母さんの心身の安定と安心は子どもへの優しさにつながる。在宅医療ではお母さんだけを頑張らせない支援が必要である。そのためには、障害のある子どもたちの家族がゆっくりくつろげる時間を取り戻せるショートステイやデイケアなどのレスパイトが欠かせないと感じていた。
「ここすまネット」のお母さん方との出会い
私がここすまネット代表の中川史さんに初めてお会いしたのは、社会福祉法人三篠会・重症心身障害児者福祉医療施設「鈴が峰」開催の2013年度厚生労働省モデル事業「重症心身障害児者地域生活支援協議会」で、もう10 年以上前である。
そのころ、中川さんは、障害のある息子さんを育てながら、福祉、医療、教育などの幅広い人達との緩やかなつながりを作り、障害のある子ども達のために活動されていた。
新生児医療に携わっていた私は医療的ケア児を育てる家族のレスパイト(特にメディカルショートステイ)の必要性を強く感じており、彼女の思いに意気投合した。
その後、メディカルショートステイ事業は、広島市の行政の理解や事業管理者、舟入市民病院の先生方のご努力によって2016年春にその一歩が始まった。
「ここすまネット」のホームページの開設と「ばぁば道子コラム」連載
私は2016年に市民病院を退職したが、「ここすまネット」で出会ったお母さん達や福祉・医療・教育・行政など多職種の方々との繋がりは退職後も緩やかに続いた。
2017年に「ここすまネット」がホームページを開設し、月1回「ばぁば道子コラム」の連載が始まった。コラムの連載はここすまネットのお母さん達との何気ない話の中から産まれた。お母さん達は、自分の子どもが障害を持ってしまったことに様々な思いを持っておられた。自分の妊娠から出産のこと、子どもの病気や事故など、子どもが障害を持ってしまった理由は違っても心に消えない深い悲しみと自責の念を抱き続けていた。
私は妊娠分娩中に気をつけることや防げる不慮の事故など、子育てについての情報を伝えることが必要だと感じた。
コラムは今から赤ちゃんを産むお母さん、妊娠中や子育て中のお母さん達への応援メッセージとして、子どもの事故や予防接種、妊娠中の合併症や感染症、新生児仮死、産科医療補償制度、子どもの健診の事などお母さんに知ってほしいことを書かせていただいた。
重症心身障害児者医療福祉センターときわ呉で感じたこと
私は、2020年秋から呉市にある重症心身障害児(者)施設ときわ呉で働いている。私がNICUで診ていた子どもたちも数人入所している。彼らは40歳近くになり、大人になっていたがどこか面影が残っていた。今でも障害をご両親に伝えた時のことが思い出され、ここまで頑張って育ててこられたご両親に頭が下がる。そばに行って名前を呼んで、手を触ると目を開けたり微笑んだりしてくれる。彼らは本当に無欲である。
私自身も時に様々な困難にぶつかりくじけそうになるが、障害を持ちながら困難を乗り越えて生きている子どもたちの姿から「大丈夫だよ。」との勇気をもらっている。
ここすまネットとのさようなら
ここすまネットが12 年間の活動を終了し、ホームページは2025年5月31日に公開を終了することとなった。彼女たちの活動は決して派手ではないが、一つ一つの人とのつながりを大切にした緩やかな力強さのある優しさに満ちていた。
ホームページの終了に伴い、令和7年4月に私のコラムは第90回で終了した。コラムは医学的な内容も多く、理解が難しい部分もあったかもしれない。月1回7年間のコラムは、私にとっても様々な情報を整理し、新しい知識を得る機会になった。この間コラムを支えていただいた中川史さん、ホームページ担当の鳥居美恵子さんを始め、他の活動メンバーに感謝している。仲間がいたから連載が継続できたと思っている。
新しい出会いとさようならの続き
ここすまネットの活動の終了に伴い、「ばぁばみちこの部屋」コラムのバックナンバーは、社会福祉法人交響のホームページにお引越しをさせていただけることとなった。
社会福祉法人交響の理事長である安部倫久さんは変わった経歴の持ち主である。通信社に勤めていた時に障害のある人と家族による共同作業所づくりと出会い、障害者福祉に関わる多くの仲間たちとともに、大切なものを一つ一つ探している。
多分、私と同じで一度見てしまって心に感じた出来事は決してなかったことにはできないではないかと感じている。そして、私も新しい出会いの中で、さようならの続きを探していきたいと思っている。
そしてこれから
人生の中で、人は何度もお別れを経験する。2016年、新生児医療の現場から離れる最後の当直の夜に、入院している一人一人の子ども達にお別れをした。「ここには戻ってこないけれど、いつまでも覚えているよ。」と。
私自身も人生の残りの時間は限られているけれど、お母さん達と「大丈夫だよ。一人じゃないよ。一緒に頑張ろう。」というメッセージをお互いに交わし合うことができれば幸せである。
「障害のあるわが子を最初は可愛いと思えなかった。」とあるお母さんは言った。「ずっと家に閉じこもっていた。」とも。周りの支えがあれば、ゆっくりでもお母さん達は心を開いて子どもに向き合っていけると思う。障害がある子どもを育てているご両親が望んでいるのは、「少しの荷物を背負って一緒に歩いてほしい」という、ごく当たり前のささやかな願いである。
医療やテクノロジーが、どんなに進んでも、人の子どもは人の手でしか育たないし、そばにいて思いや痛みやつらさ、そして喜びを分かち合うことができるのも人である。
研修医一年目のあの夏の日に見たNICUの光景と仲間とのつながりが、私の生き方の原点と道標となっていくと思っている。これからも、私のペースで、子どもたちのそばで、ささやかなメッセージを届けていくことができればと思っている。
ではまた。 Byばぁばみちこ